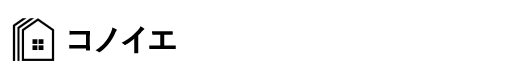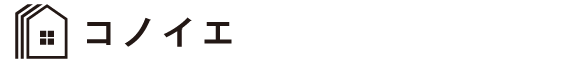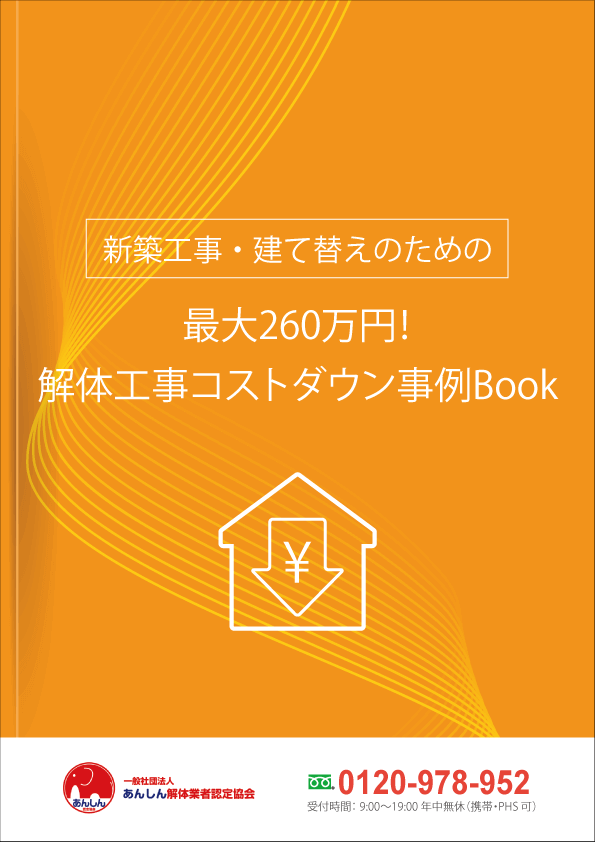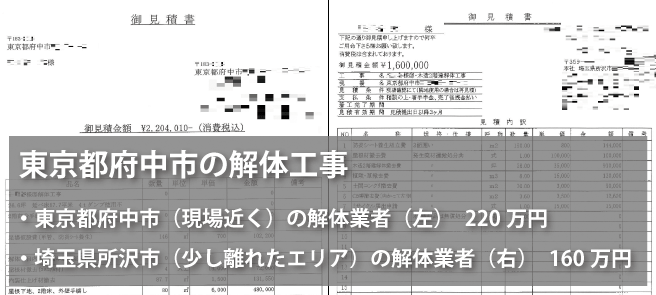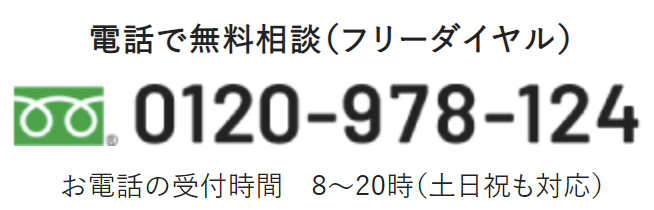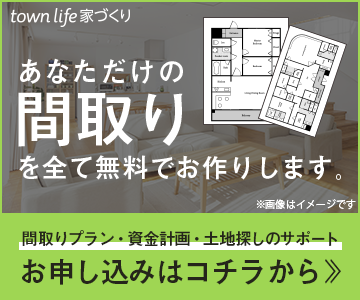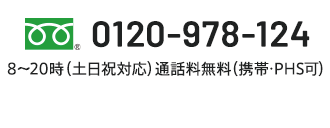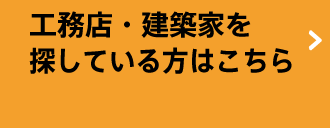そろそろ住まいを建て替えたいけれど、「今まで支払ってきた固定資産税はどうなるのだろうか?」 そんな疑問が、ふと頭に浮かんだ方も少なくないでしょう。
建て替えでは、ただでさえ高い工事費が掛かりますから、固定資産税はできるだけ安く抑えたいですよね。 実は、建て替えの時期を間違えると、固定資産税は驚くほど跳ね上がってしまいます。
本記事では、「土地」の固定資産税の仕組みや後悔しない建て替えのタイミングをご紹介しているので、これから建て替えをお考えの方はぜひ参考になさってくださいね。
住宅用地の固定資産税は、最大6分の1まで軽減される
今まで支払われてきた、ご自宅の土地の固定資産税は安く抑えられていたはずです。 それは、その土地が居住用地だったからです。
まずは、あまり知られていない、固定資産税の仕組みから確かめてみましょう。
固定資産税は、不動産の税金である
固定資産税とは、土地や建物といった不動産の所有者に課される税金のことです。
毎年1月1日の時点で不動産を所有している場合には、その年の4月から始まる1年分の固定資産税を納めなければなりません。なお、固定資産税の計算方法については以下の記事でご紹介しているので、実際の固定資産税の金額をお知りになりたい方は合わせてご参考になさってくださいね。
 非公開: 建て替えで固定資産税が上がる!?税金が高くなる原因と計算方法
非公開: 建て替えで固定資産税が上がる!?税金が高くなる原因と計算方法
住宅用地の固定資産税を軽減させる、2つの特例
土地は不動産ですから、課税の対象になりますが、住宅用地から駐車場まで沢山の種類があります。その中でも、住宅用地は私達の生活に欠かせませんから、2つの特例によって固定資産税が軽減されています。 それでは次は、これらの特例の中身を確かめてみましょう。
1つ目の特例は、「課税標準特例」と呼ばれる軽減措置です。この特例によって、所有する土地が「住宅用地」である場合には、その土地の面積に応じて固定資産税が軽減されます。
住宅用地の内、200平方メートル(60.5坪)までの部分は「小規模住宅用地」として扱われますので、固定資産税が6分の1になります。(地方税法349条の3の2第2項)
また、200平方メートルを超える部分は「一般住宅用地」として扱われますので、固定資産税が1/3になります。(地方税法349条の3の2第1項)
例えば、300平方メートルの住宅用地をお持ちの方でしたら、200平方メートル分の固定資産税は6分の1、残りの100平方メートル分の固定資産税は3分の1に軽減されることになります。
| 住宅用地 | 面積 | 軽減割合 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下 | 1/6 |
| 一般住宅用地 | 200平方メートル超 | 1/3 |
これに対して、建て替え中は、土地に建物が建っていない状態ですよね。
もしも、建て替えが完了せず、そのまま翌年の1月1日を迎えてしまうと、その土地は居住用地ではありません。 そうすると、課税標準特例が適用されませんので、固定資産税は軽減されなくなってしまうのが原則です。
しかし、建て替えについては、一定の要件を満たす場合には、例外的に課税標準特例が適用され、固定資産税が軽減されるのです。 これが「建て替え特例」と呼ばれる、2つ目の軽減措置です。
それでは、建て替え中であっても固定資産税が軽減されるためには、どのような要件が必要になるのでしょうか。建て替え特例の適用要件を詳しく確かめていきましょう。
固定資産税が跳ね上がる原因は、建て替えの時期にあった!?
建て替え特例の適用要件をまとめると、以下のようになります。
| 要件の区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| 1.利用用途 | 解体年度の1月1日の時点で住宅用地であったこと |
| 2.敷地 | 建て替えが同じ土地で行われていること |
| 3.所有者 | 解体年度と翌年度の1月1日の時点で、土地と建物の所有者が同じであること |
| 4.着工時期 | 翌年度の1月1日の時点で新築工事に着手していること |
建て替え特例が適用されるためには、これらの要件を全て満たさなければなりません。 古い住まいを新しく建て替えるわけですから、普通は「1.利用用途」や「2.敷地」の要件を満たしていると思います。
特に注意してもらいたいのは、「4.着工時期」の要件です。
もしも業者さんのスケジュールが予定通りに進まず、解体工事や新築工事の時期が遅れてしまう場合には、翌年度の1月1日の時点で新築工事に着手していなかった。 そんな最悪な事態に陥り、固定資産税が跳ね上がってしまうケースだって少なくありません。
そこで最後は、建て替え特例が適用され、固定資産税を確実に安く抑えるために、絶対に注意してもらいたいポイントをご紹介します。
新築工事は年内に着手して、固定資産税を安く抑える
これから建て替えをお考えの方に向けて、絶対に注意してもらいたいポイントをまとめましたので、さっそく確かめていきましょう。
年末ぎりぎりの建て替えは極力避ける
建て替え特例の適用を巡って一番問題になるのは、「4.着手時期」の要件です。
「雨や強風によって重機を安全に使えない」、「解体工事中に地中から埋設物が発見された」。いざ建て替えを始めてみると、思わぬ理由によって工期が延期されてしまった。 そうこうする内に翌年度の1月1日を迎えてしまい、新築工事まで着手できなかったケースも少なくありません。
参考 解体工事の期間が長くなる時期と理由 - 解体工事の情報館解体工事の情報館そうならないためにも、建て替えを始められる前には、しっかりと計画を立てることが重要になります。 建て替えの流れを把握しておくと、余裕を持って計画を立てられるはずです。
新築工事に着手する前には、解体工事や地盤調査がありますが、解体工事の工期は約1週間ほど、地盤調査の期間は約1日ほどです。
- 設計プランの決定
- 工事請負契約の締結
- 住宅ローンの申込み
- 仮住まいの決定
- 解体工事
- 地盤調査
- 新築工事
- 新居の引渡し
新築工事に着手さえすれば、建て替え特例が適用されます。 しかし、この新築工事に着手したと認められる具体的な時期は、各自治体によってその運用に若干の違いがあります。
ちなみに、東京都では、①翌年度の1月1日の時点で建築確認申請書を提出しており、②翌年度の3月末日までに新築工事に着手している場合には、「4.着手時期」の要件を満たすことになっています。
参考 住宅を建て替える土地の特例措置のご案内(東京都主税局)住まいの名義変更は親族同士にする
もう1つ問題になりやすいのは、「3.所有者」の要件です。 建て替えに際して、住まいの所有名義を合わせて変更するケースもあると思います。
この時に注意してもらいたいのが、名義変更は親族同士で行う、ということです。 解体年度と翌年度で土地の所有者が違ってしまうと、建て替え特例が適用されない場合があります。
名義変更の前後で同じ所有者と認められる具体的な範囲は、各自治体によってその運用に若干の違いがあります。
ちなみに、東京都では、6親等内の血族、配偶者、3親等の姻族からの名義変更である場合には、「3.所有者」の要件を満たすことになります。 血族とは自分側の血統、姻族とは配偶者側の血統のことです。
建て替えに伴う固定資産税についてのまとめ
建て替えが年度を超えると、時期によっては固定資産税が大幅に跳ね上がってしまいます。
そうならないためにも、特に冬から建て替えをお考えの方は、12月中に新築工事に着手できるように、業者さんとしっかりと打ち合わせをしましょう。
また、建て替え特例の具体的な運用は各自治体によって違いますから、住まわれている地域の自治体に直接問い合わせることも忘れないでくださいね。